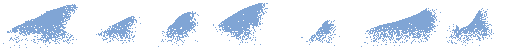旅のつれづれ
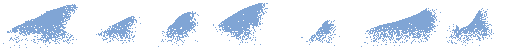
「どうしたんだ、今夜はずいぶん飲むじゃねえか。」
村はずれの小さな居酒屋のカウンターで、アリオスはその男を見つけた。
「…なんだ、おまえか。」
「ご挨拶だな。…どうした?なんか面白くねぇことでもあったのか?」
「…別に……おまえこそなんだ。またどこかに行ってたんじゃないのか?」
「ククッ、まあそんなところだ。こう見えても探求心の固まりでね。いろいろなところを探検して見ねぇことには落ちつかねぇのさ。」
「おまえが探求心というガラか。好奇心、の間違いだろう。」
「クッ、そうとも言うかな。まあいいぜ、飲めよ、オスカー。」
そう言って、自称『旅の剣士』アリオスは、共に旅をしているはずの炎の守護聖・オスカーに強い酒を注文する。
「俺の奢りだ、まあ飲め。」
「……ああ?…すまん、ごちそうになるぜ。」
「いいって事よ。」
アリオスはそう言って、自分の分の酒も注文する。
「旅の無事と…そうだな、打倒・皇帝とやらを祈って、乾杯!」
「…フッ…そうだな……乾杯。」
オスカーはもちろん、アリオスが心にもないことを祈っていることを知りはしないし、アリオスが飲もうとしている酒がオスカーの挙げた杯よりはるかに軽い酒だと言うことも気づいてはいない。
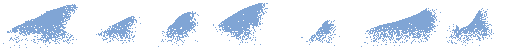
「フフ、いい眺めだぜ。」
アリオスはしたたかに酔ったオスカーを居酒屋の近くの安宿に連れ込んだ。このままオスカーが戻らなくても朝までにパーティに合流すればいいのだ。こんな時はオスカーの遊び好きが役に立つ、とアリオスは思う。
「遊び好き、か。…ククッ、それも本当はカムフラージュ……ってか?」
オスカーは今、鬱陶しいマントや上着を脱がされ、体の線のはっきりわかるプルオーバー一枚と細身のズボンだけを身につけ、ベッドに横たえられていた。上着を着ているときにはわかりはしないその細い腰。上気した白い肌に炎のような緋い髪。
「…まったく、色っぽいぜ。誘ってるつもりか?…おい。」
そろそろ、酒に仕込んだ薬の最初の効き目が切れる頃だ。強い酒と併用すると、まず二時間は正体もなく眠りこけ、目が覚めたあとは……。
「ぼちぼち、仕掛けておくか。…おまえが色っぽいのが悪いんだからな、オスカー。…今夜は別に他意もなく抱いてやるんだからありがたく思えよ。…俺が本気だったらおまえは殺されても文句は言えねぇんだからな。………皇帝とやらに、よ。」
そう言いながらアリオスはオスカーの腰のベルトをシュルっと抜き取ると、両手首を掴んでベッドの柵に軽く括り付ける。軽くとは言っても、ちょっとやそっとでは外れることはない。アリオスが『皇帝・レヴィアス』の魔力を少し用いてその戒めを強固にしたからだ。
「……さてと、あとは目が覚めるのを待つだけ、か。ちょっと銜えてやりたい気もするけど、あとのお楽しみが減っちまうからな。」
「…んん……ジュリ…アス…さま……」
「…クッ、ジュリアスさま、か。…まったく健気なもんだぜ、長い時間ずっとそばにいて手も出せない最愛の人、ってわけか。可哀想に。…と、そろそろお目覚めのようだな。」
そう言ってアリオスはそっとオスカーに覆い被さり、その唇に自分の唇を重ねた。
「ンン……ンぅ…ンンン…!?」
「…よう、お目覚めか……オスカー。」
アリオスはオスカーのそのアイスブルーの瞳が見開かれたのを認めてから、ゆっくりオスカーから唇を離した。
「ア……アリオスっ?!…いったい……なッ?」
オスカーは自分の置かれている状況に気づき、戸惑ったように言った。
「ああ、オスカー。ちょっと仕掛けさせてもらったぜ。けど大丈夫、おまえの悪いようにはしねぇよ。きっといい気持ちにさせてやるから俺に任せとけ。」
「な……なにをバカなことを!…アリオス、おまえがやったのか?悪ふざけも大概にしろ。すぐこれを外すんだ!」
「あー、暴れない方がいいぜ。腕が痛くなるだけだ。なに、ちょっと我慢してくれりゃあすぐいい気持ちになるからよ。」
「なにを……んんッ!?」
いきなり大きく開いたオスカーの口の中に長い指が入って来た。アリオスの左手の指が三本、オスカーの喉の近くにまで突き入れられる。オスカーはいきなりの刺激に思わず吐き気を覚え小さく咽せる。だが容赦なくその指は口の中に出たり入ったりを繰り返し、オスカーの舌はその指を味わいはじめた。
そうしているうちオスカーは吐き気とは別の何かがだんだん自分の理性を侵し始めているのに気づく。…それにしてもおかしい。なんで俺は抵抗できないんだ。…そんなことを思いながらもオスカーの体は快感を感じ始めた。
「そうそう。うまいじゃねぇか。そうやってしゃぶっていればいいんだ。ああ、三本じゃあ辛いんなら二本にしてやる。そう、舌を使うんだ。……ほら、だんだんいい気持ちになって来たろ?…よし、いい子にしてたらこっちも弄ってやるから。」
そう言いながらアリオスの右手が、きつい服の上からオスカーの股間をまさぐり始めた。
「うッ、う……んん、んぅ……」
「そうだ、そうやって腰を使うと気持ちいいだろ?……ああ、こんなキツいもん履いてたら痛ぇか。…わかった、脱がせてやるよ。ほら。」
「ふ……んん……んく…ぁ……ッ」
「…いい声で啼きやがるぜ、まったく。ああ、だんだん俺もキツくなって来た。けどおまえはまだきっとあっちの方を使ったことねぇだろうし、いっぺんイかせてからの方がうまくいきそうだからな。俺はちょっと我慢しねぇと。…ほらよ、もっと気ぃ入れてしゃぶりな。…ああ、こっちもすっかり硬くなってきたな…そろそろ下着も取ってやるか。」
アリオスの指がオスカーの口の中を別の生き物のように這いずり回り、オスカーは口の端から銀の糸をたっぷりと滴らせながら白い頬を真っ赤に染めて快感を味わっているようだった。
アリオスはオスカーの下履きをすべて引きずり下ろし足首の方に纏めたまま、その下から出てきたすっかり硬くなったモノを根本から揉み解すように刺激する。
「アッ!……ひッ……あ、ああッ…も……も、い…ッ……」
「…まだ達くなよ……これくらいでッ…今こっちの方を…使えるようにしてやるからな……ッ」
アリオスは右手でオスカーのそれを掴むと口から指を抜き取って、たっぷり唾液に濡れたそれを右手で掴んでいる場所の下にある堅いつぼみのような場所に、ゆっくりと二本差し込んだ。初めての感覚に耐えられないのか、オスカーのからだがガクガクと震える。
「ひッ!……い、痛……ッ……はあッ……や…やあッ…!」
「大丈夫だよ、痛ぇのは最初のうちだけだ。すぐ気持ちよくなるって。」
銜えるモノのなくなったオスカーの口がぱくぱくと何かを求めている。アリオスは堪らずオスカーにのし掛かり、再び口づけてその舌でオスカーの口を塞いだ。
痛みによって少し萎えたオスカーのモノから右手を離し、その手でオスカーを抱き起こそうとするがその腕の戒めがそれを邪魔する。
「ちっ、めんどくせぇ。」
そう言ってアリオスはせっかく仕掛けた戒めを解き、オスカーを抱きかかえた。すでにアリオスもオスカーが欲しくて堪らなくなって来ている。アリオスはオスカーの口を枕の縁を噛ませるようにして塞ぐ。
「すまねえ、本当は一度イってからと思ったけど、もう俺、我慢できねぇみてぇだ。」
そう言いながらアリオスは自分の下履きの前を一気に下ろすと、そこから出て来た猛るモノを指二本抜き取ったばかりのまだ開き切っていないつぼみに一気に突き入れた。
枕に塞がれたオスカーの口から、声にならない悲痛な叫びが空気と体を伝わってアリオスを突き刺す。
オスカーの見開かれた瞳から大粒の涙が伝わり落ちる。
「……やっぱ痛ぇよな。…すまん、マジですまん。せめて魔導で痛みは消してやるから勘弁してくれ。…ああ、こんなに血が出て…やっぱり事を急ぎすぎたよな。…けどよ、おまえが色っぽすぎるからいけねぇんだ。」
アリオスはオスカーの出血したその場所に軽く手を当て、小さく呪文を唱える。オスカーの苦痛に満ちた表情が少し和らいだ。アリオスはほっとした表情を見せながらそれでもオスカーの中に自身を埋めたままゆっくりと動き始めた。
「あ、あッ、ああ、あッ、あん、い…いッ…」
「オスカー、おまえ、最高だぜ。…ッたく、罪なヤツだぜ。」
勝手なことを言いながら、アリオスは再びオスカーの口腔を弄びながらもう片方の手でオスカーのモノを刺激する。痛さに萎えたそれも硬さを取り戻し、いつしか先端を濡らし始めた。
「そろそろ……イってもいいぜ……ああ、キツ…俺の方が…もッ…達きそ…ッ…」
「あ、ああ…も…達く……はッ…あぁ…ッ…イ…」
「あ、俺、達く……も、出る……ッ」
「い、達く……あ、ああッ……ジュリ…アス……さ……まッ…!!」
「なにッ………あ…く………!!」
アリオスはついにその精をオスカーの中に注ぎ込み、オスカーもまた愛しい人の名を呼んで果てた。
オスカーは目を閉じて、アリオスの腕の中に沈むようにしながら大きく息を弾ませている。
アリオスはそんなオスカーの官能に満ちた表情を見ながら大きく溜息をついた。
(……ジュリアスさま……か。…まったく、あいつ……。くそッ、もったいねぇ!もったいなさ過ぎるぞ、ジュリアス!…ちくしょう!…うらやましいぞ、ジュリアス!)
「……ジュリアスさま……いィ…」
自分の飲ませた薬がどう効いたのか、オスカーはすっかりジュリアスに抱かれていると思いこんでしまったかのようだ。
アリオスは再び大きく溜息をつき、オスカーの頭を小さく小突く。
「この野郎。」
すっかり毒気を抜かれたらしいアリオスは、自分とオスカーの服を元に戻すとオスカーをベッドに横たえ毛布を掛ける。そして隣のベッドサイドに腰を掛けると三度大きく溜息をつき自分も寝床に潜り込んだ。
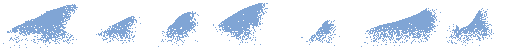
「……いったい、俺はどうしてこんなところで寝ているんだ、アリオス。」
「…うるせえ!おまえが酔っぱらって寝込んじまったから、仕方ねぇから近くの宿を取ったまでだ!これに懲りて深酒はやめるんだな、オスカー。」
朝目が覚めたときオスカーはすっかり昨夜のことを忘れているらしかった。アリオスはふて腐れたままそう答える。
「……そうか。すまなかったな、アリオス。」
「……い、いや、……いい。」
オスカーは素直にアリオスに謝る。その顔を見ているとまたアリオスはオスカーが可愛く思えて仕方がなくなって来た。
(ちきしょう。…ジュリアスめ、少しは気づいてやれよ、こいつの純情。)
「とにかく、アンジェリークたちのところに帰ろうぜ。あまり遅くなると心配するからな、あのお節介どもが。」
「…あ、ああ。すまんな、アリオス。」
そう言いながらオスカーは少し不思議そうな顔をして腰をさすっている。痛みは魔導で消したはずだがまだ少し感覚は残っているのかもしれない。アリオスは少し嬉しいような気もした。
(まあ、いいか。なんにしろ俺があいつの最初の男になれたんだし。もうもういっぺん抱くほど時間がないかもしれねぇけど、あいつの体は俺のこと、少しは覚えていてくれるかもしれねぇからな。フフ…)
そう思いながらアリオスはオスカーの肩をぽん、と叩くと、一緒に歩き出した。
…また『皇帝を倒し、宇宙を救う』旅を続けるために。
おしまい。
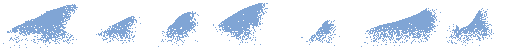
戻る