銀の盃 13
世の中も憲兵隊内も、バレンタインデーを過ぎ、その話題から落ち着いてきた頃、
クリストファーは夕方に、隊長の元を訪れた。
今日のこの時間帯は、彼にとっては勤務時間外だった。だからクリストファーは、
私服を身に纏っていた。
この白っぽい金髪の中佐は、あまり語らないが、男爵家の次男である。
当然、身につけるものなどは、さりげなく上品なものを選ぶ傾向にある。育ちが良いという
やつだろう。
彼の、決して派手ではないが立派で見栄えも良いコートを眺めて、育ちの良さなど
私には、どうあがいても手に入れられない能力だな、と、シルバーは小さく嘲笑する。
わざわざ時間外に何をしに来たのだろう、とシルバーが思っていると、
クリストファーはこう、切り出した。
「隊長、明日、18日は私の誕生日なのです。」
あぁ、知っている。おめでとう、と黒い髪の憲兵は言う。
シルバーは全員とは言わなくとも、部下の大半の誕生日は覚えている。
誕生日が来たことで、また1年「生きながらえた」と思え、命をかける仕事をして
いるからこそ、それがありがたいのだと思うべきだと、考えているからだ。
誕生日なのだということを告げてから、クリストファーは相手に向かって、言った。
「そこで、隊長。
明日の晩の、食事に誘ってもよろしいか。」
そして彼は小さく手を前に出す。尋ねている、という手振りだ。
シルバーはこの時、クリストファーの細かい「言葉遣いの変化」に気づかなかったが、
彼はあえて「よろしいか」という言葉を使ったのだ。
元より、シルバーより階級の低いクリストファーである。
尋ねるなら「よろしいですか」と聞くべきところを、「よろしいか」と告げた。
それはわざわざ、時間外に相手を訪ねてきていることにも、関係する。
この時クリストファーは、”隊長”と相手を呼んではいるが、
上司と部下ではなく、一人の男として、シルバーに誘いをかけていたのだ。
だから「よろしいか」と、敬語を使わずに、告げた。
シルバーより1歳だけ年上の、ただの一人の男として。
時間外に、私服を着て現れたのも、その為だ。
食事に誘っても、という中佐の言葉に、シルバーは返事より先に、疑問に思った点を尋ねる。
「クリストファー、バレンタインも過ぎた所だ。
お前の誕生日なら、食事を一緒にしたいという女性が、たくさんいるだろう?
それを、私などとの食事で、”日”を潰していいのか?」
純粋に分からないと言った風な表情を見せるシルバーに、クリストファーは答えを与える。
「私は、隊長と、食事がしたいのです。」
そう、相手が問題なのだ。シルバーであることに、意味がある。
それはこの、凛々しき黒髪の憲兵に、クリストファーが想いを寄せているからで、
「野暮な質問」をされたのは、自分が想いを告げていないからだ。
・・・他の皆はどうやら二の足を踏んでいるようだが、私は、行動に移す。
そう、クリストファーは思っていた。
彼自身が敬愛するエドワルド、それに、副隊長のリッテルも・・・
冷静な目で見れば、隊長に恋焦がれているのは、明らかだ。
そもそも、この人に惚れない方が難しい。クリストファーは、そう考える。
ともかく、他人はどうあれ、クリストファーは「自分の誕生日」と言う絶好のチャンスに、
想い人を食事に誘いに来たのだ。
シルバーはしばらく、顎に手をやっていた。考えているのだ。
そんな相手の様子に、クリストファーは無言で、ただ待っていた。
しばらくしてから、シルバーは答える。
「分かった。明日の晩だな?覚えておこう。時間と場所は?」
8時に××で、とすぐに日程の段取りを与え、クリストファーは続けざまに言う。
「隊長、私は”一張羅”で参りますから。」
それを聞いてシルバーも、
「・・・あぁ。私も出来るだけ、良いものを着て行く。」
と、答えることになる。
これは、クリストファーの「作戦」だった。
シルバーはとかく、部下たちと会う時、勤務時間外であっても軍服を着ていることが
多い。
私服を着ていること自体が少なく、軍服が一番肌に合うと本人が言うのだから
しょうがないのであるが。
クリストファーにしてみれば、折角の「デート」なのに、相手がいつもの軍服では、
雰囲気が出ないではないか。
だから強制的に私服着用を義務づけるように、あんな発言をした。
クリストファーは元々、かなり知的な男である。こういった頭の巡らせ方は、おそらく隊内で
一、二を争うほど優れている。
***
挨拶をして別れた2人は、約束通り次の晩、一緒に食事を取った。
もちろん食事をしただけで、その後どこにも行かない。食事中に多少アルコールは
含んだが、2人とも、酔ってはいなかった。
「とても楽しい夜でした。」
とクリストファーは言い、相手にお辞儀をする。
あぁ、私も楽しかった、また、な。と言う「上司」に向かって、白っぽい金髪の
青年は、最後に、こう告げた。
「・・・良い夢を。」
シルバーは、同じくらいの背丈の相手が、顔を寄せたことに気がついた。
だが、気がついただけである。その後、何も出来なかった。
ちゅっ
わざと、こどもがするような可愛らしい音を鳴らして、クリストファーは相手に口づけた。
これは彼の勘だったが、構えなくてもシルバーは、殴ったりはしてこないと思っていた。
事実、クリストファーが顔を離すと、そこには呆然としているシルバーがいるだけで。
そんな想い人の様子に、小さく微笑んでから、クリストファーはもう一度お辞儀をして、
その場を去った。
翌日クリストファーは、同じ歳の親友に、殴られた。
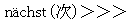
「創 作」
サイトTOPへ