銀の盃 4
「ラズベリーのタルト事件」
ノエル・シルバー 中佐、21歳。
クロード・リッテル 大尉、26歳。
エドワルド・ストーンズ 准尉、19歳。
憲兵は今日、子供と母親のための何とか会、が開かれている会場の、警備に来ている。
といっても、ほとんど子守りに近かった。
そこらじゅうで泣いたり、わめいている子供の世話をするのに走り回っていた。
シルバーは昔、産婦人科病院の警備の仕事をしていた時期がある。
周りにコネもないため、そんな昇進の望めないような場所に、配置されたのだ。
そんなシルバーに、あることを教えてくれた人物がいた。
「中佐あたりまでなら、”ペン”で上がることが出来る。
毎年、とにかくレポートを出すのだ。
佐官まで上がったら、それなりに自分の好きに動くことが可能だ。
それからだ、お前の人生は。
お前は若い。能力もある。
・・・お前の未来に、期待しているよ。」
それはシルバーが唯一「閣下」と呼ぶ人物なのだが、今は隠居していて、姿を現さない。
リッテルやエドワルドも、会ったことがない。
ともかくシルバーは、そのような方法で中佐まで昇格し、やっと小隊を持つことが
出来たのだ。
課せられた使命が子守りなどというくだらないものであっても、それを文句言わずに
こなさなくてはならない。
自分達はこんなところで終わったりしないと、思っていたから。
意味の無い仕事場だったと思っていた産婦人科病院だったが、シルバーは今、
そこに勤めていた時期が、無駄にならなかったな、と実感した。
産婦人科病院にいたので、子供の扱いに慣れていたのだ。
産婦人科というのは赤ん坊のいる場所だが、赤ん坊にかまいっぱなしで、上の子を
ほったらかしにする親は多かった。その子供達の遊び相手になったりしていたので、
子守りは得意だと言える。
しゃがみこんで、子供と目線を合わせて、シルバーは子供の面倒を見ていた。
子供相手ということで、シルバーも気が緩んでいたのだろう。
そして、それは起こった。
シルバーの腰のさしてある銃を、4歳くらいの子供が取ってしまったのである。
そしてその子供は、水鉄砲か何かのつもりでか、引き金を引いてしまった。
ホルスターの開閉ベルトをしっかりかけておかなかったのも、
発射に対してのロックをかけておかなかったのも、すべて不注意が起こしたことだ。
本当に、気が緩んでいたとしか、いいようがない。
被害者が己だったのが、せめてもの救いか、とシルバーは思った。
これで他人が怪我していたら、始末書どころの騒ぎではない。
そんな事を刹那考えている間に、シルバーの右腕からは、どくどくと鮮血が流れる。
銃から放たれた光は、憲兵の右腕をかすっていたので。
「リッテルー!!」
シルバーは大声で叫んで、どこかにいるはずの、自分の副官を呼んだ。
離れた場所で、戸惑いながらも自分なりに努力して、子供達の相手をしていたリッテルは、
声を聞いて飛んできた。
まず、床に血溜まりが出来ていることに驚き、次にシルバーが怪我をしていることに驚く。
「隊長!大丈夫ですか!」
彼はそう言って、すぐに手当てをしようとしたが、それを、
「先に、その子から銃を取り上げてくれ。」
とシルバーは遮り、副官の彼はそれに従う。
「リッテル、髪を束ねている布をとってくれるか?・・・すまない。」
シルバーは黒い長い髪を首元でひとつに縛り、白い包帯でぐるぐると巻いている。
これが一番動くのに邪魔にならず、経済的であると判断したからだ。
包帯の1つを取ってもらい、それで、自分で腕の根元を縛る。
そして、リッテルに言った。
「エドワルドに、その子の親を探すように言っておいてくれ。」
シルバーは、医務室に向かった。
リッテルに頼むことも可能だったが、それでは「隊」の役割をしなくなるからだ。
自分がいないときは、副隊長の彼に。
それは純粋に、己の部下達を信頼している証で。
***
手当てを終えて、右腕を吊って戻ってきたシルバーは、リッテルとエドワルドの側に、
13歳くらいの少女がいることに気づいた。
少女はシルバーを見るなりいきなり、
「弟がなんてことを・・・ごめんなさい!!」
と言った。半分泣いている。
「泣くことはありませんよ、お嬢さん。」
そう、シルバーはなだめるように言って、左の手で、彼女の肩に触れた。
少女は、依然涙いっぱいの瞳で、こう尋ねた。
「あ、あの、弟は、何か罰せられるのでしょうか・・・。」
一般的に考えると、未成年者の犯罪はその保護者にも責任があるといえる。監督不行き届き、と。
しかし今回の事件は、はっきりいって全て自分の不注意が引き起こした事件だし、あんな小さい子供に
責任を取らせることももちろん出来ないし、かと言って、他人にも銃で負傷者が出ているのを
見られているので、もみ消しにも出来ない・・・と、シルバーは思い悩んだ。
少し考えたあと、シルバーはこう言った。
「えぇ、罰せられます。」
それを聞いたリッテルとエドワルドは、ひどく驚いた顔をしたのだが、少女の目には
入らなかったらしい。
「弟さんを連れてきてください。」
とシルバーは言い、少女は駆けていった。
2人が質問をしようとするその前に、シルバーは副官の彼に、告げた。
「リッテル、今から言うことを、文書にして書いてくれ。それらしく見えれば、よいから。」
***
少女が、シルバーを撃った子供を連れてくると、憲兵隊長は左手にリッテルの書いた文書を
持って、それを、わざと重々しく読み上げた。
「汝、憲兵の武器を取り上げ、それにて憲兵の右腕を撃ち、
負傷させし罪、許しがたく、よってここに罰則を命じる。
汝の最も好む菓子が家庭にて出し時、一度その半量を
取り上げる。
以上。」
リッテルは身体を曲げて、少女と目線を合わせてから、相手に聞いた。
「その子の、一番好きなおやつは何ですか?」
「えっと、ラズベリーのタルトかしら、母さんの作る・・・。」
「それでは、今度おうちでそれが出たら、半分、この方に持ってきてもらえます?」
「え、それが罰なんですか!?」
少女は驚いている。リッテルはにっこり微笑んで、告げた。
「はい。特別なんですけどね。」
「ありがとうございます!」と少女は何回も言って、弟の手を引いて、帰っていった。
「必ずタルトをお届けしますから!」と叫んで。
あえて罰を与えることで、当人とその姉に、無駄なトラウマを作るのを防いだ。
右腕を負傷している相手に向かって、エドワルドは言う。
「隊長は、お優しいですね。」
するとシルバーはフフと笑って、
「私は、女子供には優しいんだ。男には、そうではないがな。」
と告げた。
「私はしばらく字が書けないから、リッテルは代筆をしてくれるか?
エドワルドは、負荷の増えたリッテルの、補佐をするように。」
はい、と2人の青年は答えた。
そのひとは、なんと強く、優しいのだろう。
彼らは、あらゆる場面でつくづくそう実感することとなる。
そうして、幾人かの青年の心の内で、想いのたけは大きくなっていくのだ。
「ラズベリーのタルト事件」終
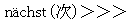
「創 作」
サイトTOPへ