午睡〜ひるね〜
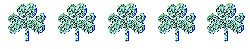
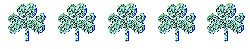
ジュリアスは宮殿の長い廊下を歩いていた。
いや、歩いていたというには早足過ぎる。小走りといっていいかもしれない。仕方がないのだ。この小さな体で広い宮殿を行き来するには、歩いていたのでは時間が無駄になりすぎる。だからジュリアスはいつも、宮殿をできる限り速く歩いていた。その日も同様である。
ジュリアスの向かっていたのは、彼の一番好きな、闇の守護聖の部屋。
優しくて力強い、幼いジュリアスのよき話し相手であり、よき師でもあった。
闇の守護聖の執務室の前に立つ。
だが今日は何かいつもと違う。
……闇のサクリアが強い。ここのところ翳りが見えてきたのかとジュリアスはいつも気にしていた、そのサクリアの力がとても強い。
(よかった…あの方の力はまだまだ続くのだ……!)
そう思ったジュリアスは、力強くその扉を開いた。
誰もいない……。
灯りのない薄暗い部屋には誰もいない……
…いや…そうではない。
ジュリアスは目線を下げた。
そこにいたのは…自分と同じくらい……いや、もう少し小さく見える…少女か少年かわからないが、黒い髪を肩で切り揃えた……。
「そなた……いったい…何故、ここにいるのだ?」
そう問いながら、ジュリアスは理解していた。この強い闇のサクリア。
幼いながら守護聖中で最も強いサクリアの持ち主であるジュリアスにはわかる。
(新しい……闇の守護聖。)
それにしても強いサクリアである。ジュリアスと拮抗するほどの……。
「そなた……新しい闇の守護聖か……?」
「………」
「この部屋にはそなたのほかには誰もいなかったか?」
「………」
「黙っていてはわからぬ!返事をせぬか!」
「……わからない…」
「なに?」
「ぼくは…しらないひとにここにつれてこられたんだ。だから、なんにもしらない。」
「……そうか。……まだどこかにいるのかもしれない……。邪魔をしたな。」
ジュリアスはそう言って、急いで部屋を出た。
(あの人に……まださよならも言っていないのに……)
ジュリアスは走った。厩舎まで走って馬を駆り、聖地の門まで行った。
だがもう、誰もいなかった。
ジュリアスは泣いた。
父や母と別れた時さえ泣きはしなかったのに。
何故、自分に黙って行ってしまったのだ。どうして……あの人は……。
翌日、ジュリアスは改めて闇の守護聖・クラヴィスと引き合わされた。
だが苛ついていた彼は結局、ろくな挨拶もできないこの少年と、黙って先代の闇の守護聖と自分を引き離した大人たちに腹を立て、癇癪を起こした。
そういうわけで、この双璧の守護聖の出会いは、最悪の滑り出しとなったのである。
ジュリアスはだが、すぐに考え直した。
守護聖の交替は仕方のない事。最後にきちんと別れをさせてくれなかった大人たちには腹も立つが、それはクラヴィスになんの罪もない。
礼儀もわきまえない者、とは思ったが、相手はまだここに来たばかりの小さな子供ではないか。
あの子は自分とは違う。何も知らない、わからない、と言っていたではないか。
(私が一から教えてやればいいのだ。)
だが……と、ジュリアスは思う。
あの子の力はなんなのだ。自分が聖地に来たばかりの頃でさえ、先代の闇の守護聖は、あのような強いサクリアは持っていなかった。
もちろん他の守護聖も。
自分のサクリアの強さに敵う者はいない、と密かに誇っていた、その力に勝るとも劣らない力を持つ、クラヴィスという少年。
闇色の髪と、紫水晶の瞳。
自分にない…いや自分とは正反対の、闇の属性。
何故……何故、こんなに……気になるのか。
わからないままに、ジュリアスはクラヴィスにこだわり続けた。
その理由がなんであるのかわからないままに……。
「クラヴィス」
「…………」
「クラヴィス、眠っているのか!?」
「……ん……?」
「また眠っていたのだな?そなたはいったい勉強をする気があるのか。そなたが勉強を教えて欲しいといったから、私はこうしているのではないか。そなたが寝ているのでは、私は何のためにここにいるのかわからないではないか!」
「ジュリアスもいっしょにねむればいい。」
「…なんだと?」
「きもちいいからいっしょにひるねをしよう、ジュリアス。」
「きもちいい……って……そなたはいったい何故そのように眠れるのだ?……まったく信じられぬ!」
「だって…ねむいんだもの…。」
「私は夜きちんと寝ている。それで十分なはずだ!」
「ぼくはあまりねむれないんだ。」
「どうしてだ!?」
「……わからない……」
「なにっ?」
「……ジュリアスはどうしていつもそんなにおこっているの?」
「……そなたが怒らせるからであろう!」
「ジュリアスはこわいよ…」
「なんだと?!」
「ほら、そうやってすぐおこるし、こえはおおきいし…」
「…………」
「ぼくはやっぱりジュリアスといっしょにいるのはいやだ。」
「……クラヴィス…」
「うちにかえりたい……」
「クラヴィス…!」
「………」
「もう……そなたの生まれた星には帰れないんだ。守護聖になりたくないなんていっても許される事ではないんだ。私たちは、そういう運命なのだ!私たちは……っ」
「ジュリアス……?」
「…………」
「どうしたの?ジュリアス…ないているの?」
「泣いてなどいない…っ」
クラヴィスはジュリアスの顔を覗きこんだ。確かに、ジュリアスの目には涙はない。
ジュリアスは目も口もぎゅっと力を込めて閉じているようだ。
「ジュリアス…」
ジュリアスは口を開く。
「そなたが私を嫌いなら、それでもかまわない。だが、守護聖としてのつとめは果たさなければならないんだ。そのためにはちゃんと勉強して、立派な人にならなければいけないんだ……誰よりも立派な…守護聖に…」
ジュリアスは閉じていた目も開いた。瞼の間からあらわれたサファイアの瞳に、クラヴィスは吸い込まれるような気がした。
(ジュリアスは…いまのことばをじぶんにいっているのじゃないのかな…?)
そんな気がして、クラヴィスはジュリアスを見つめた。
そして、ジュリアスもクラヴィスをまっすぐに見つめた。
「クラヴィス。私たちはまだ小さい。けれど、光と闇の守護聖だ。他の守護聖をまとめていかねばならない大事なつとめだ。それを、わかってほしい。」
「ジュリアスは……あたまがいいから…。ぼくは、あたまがわるいんだ…きっと…」
「何を言う。そなたは頭が悪くなどない。ただちゃんとした勉強をしていなかっただけなのだ。私と一緒に学ぼう。……私が嫌いでも…かまわないから…」
「…ぼくは、べつにジュリアスのこと、きらいじゃないよ。…ねえ、ぼくがジュリアスのいうことをきいたら、ジュリアスもぼくのいうことをきいてくれる…?」
「……あ、ああ……きくとも。どんなことだ?」
「ジュリアスは…つかれてる。…べんきょうのしすぎだ。」
「なんだと…?」
「ぼくたちはまだこどもなんだから、ゆっくりべんきょうすればいいんだ。いますぐおとなのしゅごせいにおいつこうなんて、かんがえないほうがいいよ。」
「……だが……私は、早く立派な……」
いつの間にか、クラヴィスはジュリアスの握り締めた左手を、自分の両手でくるむように握っている。ジュリアスの中に、暖かいなにかが流れ込んで来る。
「ジュリアスは、りっぱなしゅごせいになれるよ。だから、むりをしちゃだめだ。……びょうきになるよ。びょうきになったら、いいしゅごせいになるまえにしんじゃうよ。」
「聖地では、陛下のお力で、病気などにはならぬはず…」
だがジュリアスはさっきまで体中がこわばって、とても疲れていたような気がした。でも、クラヴィスの手から流れ込んでくるなにかが、それをどんどん癒してゆく。
「いまはやすもうよ、ジュリアス」
ジュリアスは眉を顰め、口をへの字に曲げながら不承不承答えた。
「今だけだぞ……」
「ふふ…」
クラヴィスは、ジュリアスの手を引いて、部屋の隅にある長椅子にジュリアスを導く。そしてクッションをぽんぽんと叩いて、ジュリアスを掛けさせ、自分も腰掛けた。
「ここで、ひるねをしよう、ジュリアス。このいすは、とてもきもちがいいよ。」
ジュリアスは答えなかった。見ると、小さく頷いてはいるものの、もう目が開けていられないようだ。次の瞬間には、ジュリアスはクッションに頭と背中を埋めて、小さな寝息を立てていた。
クラヴィスは、それを見てにっこりと微笑んだ。
それは、初めて自分の闇の力が何かの役に立った、とクラヴィスが自覚した出来事でもあったのだった。
「おやすみ、ジュリアス。」
そう言って、満足そうに微笑みながら、クラヴィスはジュリアスに寄り添うようにして眠った。
――安らぎの中で。
おしまい。
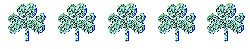
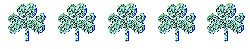
長らくお待たせして、この体たらく…ぺけぽんさん、ごめんなさい。
でも最後は、ぺけぽんさんのところからいただいて来たバナーの
二人を思い浮かべながら書きました。
眠くなってくれれば幸いです。(えっ?そうなの?)

