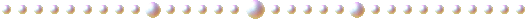真・虜
ここは、どこだ…。
ジュリアスはゆっくり目をあけた。宮殿か?いや、違う。わからない。頭ががんがんする。どうやら後ろ手に縛られているようだ。ジュリアスは、軽く頭を振りながら、そうっと周りを見まわした。そしてそこで見つけたものは、信じられない光景。
壁に鎖でつながれた、女王・アンジェリーク…ぐったりとうなだれてはいるが、ピンクの女王の衣装の胸がゆっくりと動いている。無事ではあるようだが…と…そして、もう一人いる…それは…その姿は…。
「そなたはいったい…」
長い波打つ金の髪、細身の長身に広い肩幅、陶器のような白い肌に形の良い眉が…しかし、それは本来の持ち主とは違って、幾分歪んでいるようであるが…そして切れ長の鋭い瞳は…それがもっとも違う点ではあるが…真っ赤な血の色に光っていた。
そう、彼はジュリアスと瞳の色以外まったく同じ姿をしていて…そしてまったく似てはいなかった。
「ようやくお目覚めのようですね、光の守護聖どの。」
彼はジュリアスと同じ…なのだろうか、やはりまったく違うようにも思えたが…声でそう言うと、醜く引きつった笑いを口の端に浮かべて、床に転がっていたジュリアスの頬をその長い指で撫でた。
「ふっ。なんと言う美しさなのでしょうね。この金の髪といい、このビスク・ドールのような肌といい、このサファイアの瞳といい…。完璧です。私をあなたの姿に作ってくださったあの方に、感謝しますよ。」
「そなたはいったい誰だ。何の為に陛下や私を拘束するのだ。…あの方、とは誰だ。」
ジュリアスの姿をした男は、クックッと笑ってから、こうすらすらと答えた。
「私の名は、キーファー。今はそれ以上はお教えできません。あなた方を拘束した理由はこれからわかります。あの方のこともいまはまだお教えする時ではないようです。」
「たわごとを申すな…っ!」
そのとき突然背中に電気を流しでもしたような痛みが走って、ジュリアスは呻いた。見ると、キーファーと名乗る男の手に、乗馬用の鞭が握られている。
「失礼。私は手が早くてね。あまりおかしな事を言わない方が、あなたのためですよ。私は今はあなたの命までとろうとは思っていませんからね。…ただ、その美しい顔が苦痛に歪むのを見てみたいとは思っていますが…ククク…」
ジュリアスはこの男が、今まで見たこともない種類の人間だと判断した。背筋に悪寒が走る。この男は、危険だ。
「さて、と…。そろそろ本題に入りますか。まずは、女王陛下。」
キーファーは鞭の先でついっ、と気を失っている彼女の胸のふくらみを押した。わずかにアンジェリークは呻き声を漏らす。
「陛下…っ!よせ、陛下に触ってはならん!」
「ククク…そうおっしゃると思っていました。光の守護聖どのの女王陛下に対する忠誠ぶりはあの方から聞き及んでおりますからね…。そう、それ以上の関係…も。」
ジュリアスは慄然とした。この男はいったい何をするつもりなのだ。
「女王陛下は今は薬で眠っています。まだそれ以外何の手出しもしていません。私は基本的には女性に手を出す趣味は、ない。」
ジュリアスは本能的に、嫌悪感で体が震えるのを感じた。
「ただ、できない、と言う意味ではありません。あなたが拒めば、彼女を代わりに凌辱することになります。…わかりますか?この意味が…。」
キーファーは堕天使のようなその微笑を浮かべながら、こう続けた。
「私の欲しいのは、貴方です。ジュリアス。」
いったい…どう言う意味だ…いや、わかっている。だが認めたくない。ジュリアスは体を捩って逃げようとした。だが、キーファーはそれを待っていたようにすぐそばの壁にあったレバーのようなものを引き下ろした。
がくん、とジュリアスの体が揺れて、後ろ手に拘束された手首がカチッと言う音とともに左右に別れ、鈍い痛みをともなって引っ張り上げられる。ギギギ、と音を立てて滑車が回り、ジュリアスの体は大の字になって宙に浮いた。足にも枷が繋がれている。
「うう…っ」
手首に鉄の手枷が食い込む。キーファーは嬉しそうにその様子を見て嗤った。
「素敵です、ジュリアス。その無防備な姿。さあ、まずどこからいただこうか。」
キーファーはジュリアスの頬を手で支えると、その唇に接吻した。と、ジュリアスの口の中に舌を滑り込ませ、何かを押し込んだ。そしてそのまま息が苦しくなるまで離さなかったので、ジュリアスはついにそれを飲み込んでしまった。
「な…何を入れたのだっ…。」
「ふふ、ちょっと、貴方の理性が邪魔なのでね…飛ぶクスリ、と言うやつですよ。さて、次は…どこにするかな?…そうそう、まずはこの邪魔な重い服を取りましょう。」
ジュリアスは身を捩ったが、キーファーはほとんど苦もなくジュリアスの装身具を外し、取れるだけの布を取り、残る衣服はナイフで切り裂いた。
露わにされた胸に舌を這わせ始めたキーファーに、ジュリアスは声にならない呻きを上げた。しかしそんなことはお構いなしにキーファーの舌がジュリアスを責める。
「う…あっ!」
キーファーががりり、とジュリアスの乳首を噛んだ。紅い瞳がジュリアスを見上げて不気味な光を放つ。キーファーはにやり、と笑って少し血のついた舌をぺろりと舐めずった。
「次は、そろそろ、こちらを…」
そう言って、キーファーがジュリアスの残された下着にナイフを差し込む。
「暴れると、怪我をしますよ。」
そして、あっという間にそれを切り裂き、その下にあるものを掴んだ。
「ううっ…。」
思いきりそれを掴まれて、ジュリアスは悶絶しそうになった。
「クク…どうやら少しクスリが効いて来たようですね…ほら、硬くなって来ている…。」
キーファーはその先端をぺろり、と舐めた。その初めて知る感覚に、ジュリアスのそれはびくんびくんと痙攣した。
「う…あっ…」
「いい声だ。ぜひもっと聞かせてください。ああ、そうだ…あまり早くいかれてはつまりませんね…こうしよう。」
キーファーは髪を縛っていた細い紐のようなものを解くと、ジュリアスのそれの根元を縛り、それから口を開けてそれを頬張った。
「う…う…っ…」
ジュリアスは精一杯こらえるが、クスリのせいなのか、どんどん歓喜の波が押し寄せてくるのに気付く。キーファーの舌が、ジュリアスのそれに絡み付いてくる。気持ちとは裏腹に、何度も快楽がジュリアスを襲う。体中の血がそこに集まったように脈打っているのがわかる。
「あ、ああ…っ…はあっ、あああ…っ」
その波が絶頂に達しようとした時、何かがそれを押し留めた。堰き止められた波は堪らない不快感と痛みのような感覚でジュリアスを弄ぶ。キーファーはそれに気付き口を離し、そして舌舐めずりをしてから、こう言った。
「どうして欲しいですか?いきたいのかな?それなら、貴方の口から、こう言ってください。『お願いします、いかせてください』と、ね。クククっ。」
ジュリアスは身震いした。そんなことを言うくらいなら、このまま悶え死んだ方がましだ。
「言わないのですか?ククっ…まあ、そうだろうと思いました。では、貴方ではなく、彼女にお願いしましょうか…。」
キーファーはまだ意識の戻らないアンジェリークの胸に手を伸ばし、ナイフをかざした。
「待てっ…!」
「はい、待ちましょう。どうしますか?」
「………」
「まだ足りないようですね…ああ、彼女のことを思い出したら、少し現実に戻ってしまいましたか…では、こうしましょう。」
キーファーはその長い指の一本を咥えて十分に舐め、もう片方の手でジュリアスのそれを握った。そして唾液で潤った指でジュリアスの後ろを探ると、その固くすぼまった蕾にその指をいきなり捩じ込んだ。
「うあっ!」
予想もしていなかった行為による不快感と痛みにジュリアスは叫んだ。しかしキーファーは容赦なく蕾をこじ開けようとする。ずきずきと、今度はそこにだけ神経が集中する。
「きついな…まあ、当たり前でしょうけれどね。初めは、誰でもそうですよ。」
だがジュリアスにはその言葉も遠くに聞こえた。激しい痛みが波をうって、ふわふわとした気絶寸前の浮遊感と交互に入れ替わる。
「は…ああ…あっ…」
ジュリアスは無意識に喘ぎ声を漏らしていた。痛みがだんだん、快感に変わっていく気がした。いったん治まった波がまたジュリアスを襲う。
「ふっ…くっ…んっ」
「ふふ…いい声ですね。どうやら、私もその気になってしまいました。ふふふ…失礼しますよ。んっ…」
キーファーはついに自分の硬くなったものを取りだし、背中から乱暴にジュリアスの蕾に捩じ込む。
「ぐああっ!」
ジュリアスは自分の肉が裂ける音を聞いたような気がした。じゅぶじゅぶと、湿った嫌な音がする。血と粘液の入り混じった液体が、つうっ、とジュリアスの内股を伝わり落ちる。
ゆさゆさと揺さぶられるたびに気が遠くなったり、痛みがぶり返したり、それは先ほどの指のときの同じ感覚とは比べ物にならないほどだ。そして再び痛みは快感に変わる。三度、快楽はジュリアスを苛み始めた。
「うっ…あ、あ、ああっ…」
「そろそろ…開放してあげたらどうです…。ほら…こんなに硬くなってる。…辛いでしょう?…ほら、一言…言えば…いいんですよ…『いかせてください』…って、ね。」
「い…っ」
「そう、素直になって…」
「い…わぬ…」
「クク…まったく、強情なお人だ…ほら、言いなさい…っ」
キーファーはさらに激しく突き入れた。何度も、何度も…。ジュリアスの体が痙攣してがくがくと震える。焦点の合わぬ目で床の方を見ると、血と粘液の入り混じったものは床を真っ赤に染めていた。ジュリアスはもう喘ぐ力も無くしていた。僅かに口をパクパクと動かしてはいるが、もう声を出そうとしているのか、息をしようとしているのか自分にもわからなかった。
「く…っ!」
背中でキーファーが喘いだ。ジュリアスの中に欲望を注ぎ込んで、キーファーが達した。と、同時にジュリアスの体が大きくがくん、と震えた。もう、見開いた青い瞳は何も見ていない。キーファーはそれを見て舌打ちし、ジュリアスのそれの根元に固く食い込んだ紐を解いた。
ジュリアスは何度も痙攣しながら白い飛沫を飛ばし、完全に意識を失った。
ぽつん…と、ジュリアスの頬を何かが濡らす。ジュリアスはうっすらと目を開けた。と…そこに映った姿は…。
「アン…ジェ…リ…ク…」
アンジェリークが涙に濡れた瞳で、ジュリアスを見つめている。ジュリアスは記憶を辿る。そして、あの忌まわしい出来事を一気に思い出して身震いした。
「ジュリアスさま…ごめんなさい。」
「な…いったい…あっ!」
自分のことはいい、そうだ、アンジェリークは無事なのか?ジュリアスは起き上がろうとして力を入れたが、すぐに激痛にそれを邪魔された。
「あっ、動かないでください。ひどい、怪我を…」
「あいつは…あいつはどうした…っ!」
「わかりません。気がついたら私は床に寝かされていて、横にあなたが倒れていました。…血が出てて…あ、あんなこと…っ」
ジュリアスが見まわすと、そこは宮殿の女王の私室であった。これはどういうことだ。先ほどの部屋は…夢のはずはない。こんなにまだ体が痛む。だがどうやら床に滴った血の跡もない。あの場所から戻ったのか。いったい、どうやって?
ジュリアスのほとんど全裸に近い体には、青いケープが掛けられている。アンジェリークはジュリアスの出血の場所を知っているのだろう。そして、そのわけも見当がついているようだ。さかんにひどい、ひどいと言って泣いている。
「わ…たしは…かまわぬ、そなたは…なにも…されては…」
「大丈夫です、私は服を着たままでした。も…もちろん下着もっ。」
「そうか…よかっ…た…」
「ジュリアスさまっ?」
ジュリアスはほっとしたと同時に再び意識を失った。
次にジュリアスが目を覚ましたのは私邸の寝台の中だった。付き添っていたオスカーに顛末を聞いてみると、どうやらジュリアスは陛下の私室に入り込んだ賊と格闘して大怪我をしたことになっているようだった。事実はアンジェリークの胸だけにしまったのだろう。
「それにしても、どうやってこの聖地に入り込んだのでしょうか、そいつは。」
オスカーの問いに、ジュリアスは考え込んだ。何故。何故二人はあのようなところに拉致されていたのか。何故あの男は聖地に…何故私の姿で…。『あの方』とは誰だ。本当の目的は何だ。私を凌辱するためだけのはずはない。
『いまはまだお教えする時ではないようです』
自分と同じ姿をした忌まわしい男の声が再生された。いつかもう一度…彼、キーファーとそして『あの方』は私の前に姿をあらわすだろう。そのときに、その謎も解けるのだろうか。しかしその時が来たら、私は戦えるのだろうか。いや、戦わなければならない。迫り来る、大きな力。その力から、女王陛下を、宇宙を守るために。
…だが、恐怖は未だジュリアスを虜にしている。
(いつか、いつか私はこの呪縛から解き放たれるのだろうか。)
ジュリアスにはわからない。今は…まだ。