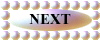>
虜・1
1.長い夜
その夜、いつものようにハープを弾きに来たリュミエールが部屋を辞していったのは夜半過ぎであった。
明日は日の曜日である。
もっとも執務が休みなだけで、いつもとどれほど違うわけではないが。
なんの用事もあるわけではない。リュミエールはどこかに誘いたそうであったが結局いつものごとく無愛想なこの闇の守護聖に遠慮したのか、挨拶のみで帰っていった。
クラヴィスはもう眠ろうとして立ちあがりつつ、何気なく手元の水晶球に目をやる。
その時つい、古い付き合いのあの光の守護聖のことを思い出してしまった。
そんなクラヴィスの心の機微を捉えたこの紫の宝珠は、望みもしない光景を瞬時に映し出した。
抱き合うようにして眠る金の髪の男と女の姿。さぞや深い眠りに落ちているのだろう、その顔はとても安らかだ。
クラヴィスは頭を振ってその映像を瞼から追い払った。
殆ど何物もクラヴィスの関心を引くことはないはずだった。しかし、そんなクラヴィスの心を強引に開こうといつも干渉して来る幼馴染みと、遠い昔の誰かの面影を呼び起こす金の髪の少女。この二人がいつしか愛し合うことになった時、クラヴィスはやはり僅かに動揺した。おそらくは誰も気づくことはなかったであろう。しかし全くなにも感じない、というわけには行かなかったのは事実である。その時心に起った感情を、なんというべきなのか。
しかしクラヴィスはそれを心中深く沈めた…つもりであった。
だが今、その感情がまた蘇った。
それは嫉妬なのだろうか。焦燥なのだろうか。わからない。今もわからなかった。あの少女の心を、伏兵である光の守護聖が思いがけず奪ったことで、自分の恋を失った守護聖も確かにいる。だがそういう言葉だけで説明しきれないなにかがクラヴィスの心にあった。
水晶球は見たいものをそのまま全て映し出すようなものではない。それはクラヴィスの心を通して映し出されるものだ。クラヴィスが何も望まないのなら、なにものをも映し出しはしないだろう。
本気で望めばなんでも見えてしまうかもしれぬほどの力を持つこの闇の守護聖は、それゆえ何にも関心を持ちたくなかったのかもしれない。それでも容赦なくクラヴィスに見えてくる事象は、クラヴィスが実は誰より人の心に敏感なことを顕わしているのだろうか。
クラヴィスは水晶球に覆いをかけると再び椅子にかけて目を閉じた。
とても眠れそうになかった。
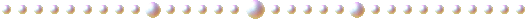
ジュリアスは何者かの気配を感じて目覚めた。
まだ暗闇に沈んでいる部屋には、隣で健やかな寝息を立てているアンジェリークがいるのみである。
それでもジュリアスは何故かあの黒髪の幼馴染みのことを思い出した。
ジュリアスがアンジェリークと結ばれたことが誰よりも意外だったのは当の本人であった。守護聖の中で誰よりも女王陛下を『崇め奉っていた』(オリヴィエ談)ジュリアスがまさか女王陛下に恋をするとは。いや、もっとも恋の相手が女王になってしまっただけであるが……。そんなわけだからジュリアスは自分にとっての凄まじい葛藤を乗り越えてアンジェリークを選び取ったのだ。彼女に恋をしていた他の守護聖たちに対しても遠慮はあったが仕方のないことと割り切った。ただ「その中」にあの闇の守護聖がいるということは、その時のジュリアスには考えも及ばないことであった。
しかし今ジュリアスは確かに彼を感じた。彼のように霊感などとり立ててあるわけではない。それでも伊達に気の遠くなるような長い年月、共に聖地に暮らしているわけではないのだ。彼の考え方は相変わらず理解できはしないが、それでもやっと、あの闇の守護聖の心の深淵にある……それをなんと言えばいいのかジュリアスにはわからなかったが……、何かを感じることができるようになって来たらしい。
これ以上考えても埒があかないと、ジュリアスは再び目を閉じて眠ろうとした。しかし眠りに吸い込まれようとした刹那、ジュリアスの脳裏にありありと浮かび上がってきた光景があった。
森の湖のほとり。まだ年若いクラヴィスが一人で立っていた時のことを。あの時は…。
…そうだった。クラヴィスは待っていたのだ。一人の少女を。
そうだ。今ならわかる。クラヴィスは恋をしていたのだ。あの金の髪の女王候補に。ジュリアスを信じて、クラヴィスへの伝言を託した少女に。
何故自分はあんなことをしたのか。何故彼女の言葉をクラヴィスに伝えなかったのか。
確かにあの時はクラヴィスに、守護聖の立場を忘れた行動に対する憤りと、自分の真意が伝わらないもどかしさを感じていた。だが伝言を託した彼女は真剣だった。きっとクラヴィスもそうだったのだろう。それなのに何故自分は…。
ジュリアスは激しい後悔と自己嫌悪に身震いした。今になってわかるとは…。もう、決して取り返しなどつかないのに。
なんと心無い行為だったのだろう。なんと酷い仕打ちだったのだろう。
それなのに自分はこうしてアンジェリークと…。
いつしかジュリアスは寝台に身を起こしていた。アンジェリークは隣で何も知らず眠っている。…だが、こんな自分が許されるのか?…こんな自分を許せるのか?
ジュリアスの握り締めた震える拳が、滴り落ちる涙で濡れていった。
2.それぞれの想い
「だからよ、昨夜すっげえ珍しい人に会っちまったんだってば。」
「珍しい人?」
「あ、ゼフェル、また聖地の外に出たんでしょ!どうしていつもそうなの?」
「うるせえなマルセル、いいだろ。でよ、誰だと思う?」
「わかんないよ、そんなこと。でも俺たちの共通の知り合いってことだよね。前にこの聖地にいた人ってこと?」
「でもあまり前だったら会ってもわからないくらい変わってるしね。」
「逆に、ティムカやメルたちじゃあなさそうだよな。だったら…。」
「今の陛下の試験の頃いた人ってこと?」
「ピンポーン!…で、ずばり誰だかわかるか?」
「……まさか…ディアさまとか?」
「お、なんだよ、ランディの癖に冴えてんじゃん!」
「ええっ?ディアさまに会ったの?」
「おう!それでよ、あの人、今でも前の女王陛下と付き合いがあるんだってよ。」
「ええっ?じゃあ、ゼフェルは陛下に会ったの?」
「でもさ、ディアさまって今幾つくらいになってるんだ?」
「うわ、一遍に訊くなってば!ちょっとおばさんになってたけど相変わらず美人だったぜ。でよ、女王陛下のことだけど、それでおめえらに話があるんだよ。」
「え、なになに?」
「俺たちまだ、前の陛下ってまともに顔も見たことねえじゃん?でよ、会いたいって言ってみたんだよな。そしたらよ、ずいぶん考えてたけど、結局会わせてくれるってことになったんだよな。」
「それはまことか?!」
「え?ええっ?ジュリアスさま?」
「げっ、ジュリアス?あんた日の曜日の朝っぱらからなんでこんなとこに…?」
「日の曜日とジュリアスさまとなんの関係があるの?」
「だからよ、土の曜日はいつもアン…陛下と……い、言わせんなよな!」
「ゼフェル、まことなのか?そなた、ディアの居場所を知っているのだな…?」
「うわ!し、知ってるよ、これから会いに行くんだよ、なんならあんたも連れてってやろうか?」
「ゼフェル、ジュリアスさまになに言って…」
「わかった。そなたについて行こう。」
「……え?マジ?」
「ジュリアスさま、それって聖地の外に出るってことですよ?」
「な…なにかちゃんとした御用があるんだよ、ジュリアスさまには…」
「いや、私事だ。ゼフェル、いつ出るのだ?」
「あ、昼飯食ってから…のつもりだけど?」
「わかった。では昼餉の後にまたここに来ればよいな?」
「あ、ああ…、そ、それでいいぜ。」
「済まぬな。」
「……あ、おい、ジュリアス!その恰好で来るなよ!ちゃんとスーツかなんか着て来ねえとダメだぞ…って、行っちゃったよ。聞こえてんのかね。」
「な、何があったのかな、ジュリアスさま…。目が赤かったような気がしたけど。」
「……お、俺ちょっと混乱して来た。」
「……ま、これで外に出たことをとやかく言わねえだろ。いいよ、行ってくるわ俺。」
「う、うん。今回はぼくたち遠慮した方がよさそうだから、ディアさまによろしくね。」「やれやれ、ヘンなことになっちまったぜ。」
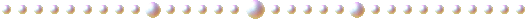
「クラヴィスさま!」
「……」
「……クラヴィスさま!?起きてください!」
「寝てなどいない。」
「……失礼しました。で、突然で申し訳ありませんが、ジュリアスさまがどこにいらっしゃるか御存知ありませんか?朝からお姿が見えないのです。」
「知らぬ…。私はジュリアスの番人ではない…。」
「オスカー!?どうしたのですか…ジュリアスさまなら、日の曜日ですし、陛下のところにいらっしゃるのではないのですか。」
「いたのか、リュミエール。それが違うんだ。先程陛下にお会いしたら、朝早く陛下のお部屋を出られたとおっしゃった。とても様子が変だったらしくて、陛下も心配していらっしゃる。だが、お屋敷にも、湖や庭園にも、もちろん宮殿にもいらっしゃらないんだ。」「様子が変…というのは、お加減が悪いと言うことなのではないのですか?」
「…よくはわからんが、お顔の色が優れなかったことは確かのようだ。」
「まさか、どこかでお倒れになっているのでは……クラヴィスさま?」
「水晶球はそう言うものではないと、何度も言ったはずだ……」
「…ですが、クラヴィスさまも本当はジュリアスさまのことが御心配なのではないのですか?……でしたらきっと…」
「お願いします、クラヴィスさま!もしなにかあの方にあったとしたら俺は…!」
「光のサクリアには異常はなかろう…」
「ですが…!」
「……これは…まさか、アンジェリーク!?」
「………クラヴィス…さま?」
「え?陛下がどうかなさったのですか?」
「ジュリアス……いったいこれはどういうことだ?」
「やはり水晶球になにか映ったのですね?」
「クラヴィスさま!ジュリアスさまはいったいどこに…」
「…外だ……。あれは今、聖地にはいない。」
「まさか!?ジュリアスさまがお忍びで外へなどと…」
「ついでに言えば、ジュリアスは前女王陛下と共にいる。場所は聖地の外という以外は解らんがな…。信じる信じないはそちらの自由だ。私は見たまでを言っただけのこと…後は勝手にするがいい。」
「……解りました。御協力ありがとうございます。では俺はこれで…邪魔したな、リュミエール…。」
「オスカー……。いったいジュリアスさまは何故…。クラヴィスさま……」
「……知らぬ。おまえももう行くがよい。」
「……わかりました。失礼いたします…。」
「………ジュリアス…いったいおまえはどういうつもりなのだ…。何故、私の心を乱す?何故そっとしておいてくれぬのだ……なぜ…。」
3.ジュリアスの異変
女王アンジェリークがクラヴィスを謁見の間に呼びつけたのは、もうすでに夕刻に近い頃だった。
「お呼びだてしてすみません、クラヴィス。私の方から行きたかったのだけど…」
「いえ…陛下。お気遣いには及びません。で、何の御用でしょうか。」
「……ジュリアスがなぜだか聖地の外に行ったと聞きましたけれど、クラヴィス?」
「……それは…オスカーの方からお聞き及びの通りです。」
「そうなのでしょうけど、でもね…私、心配なの。」
「…ジュリアスが浮気せぬかとでも…?」
クラヴィスは自嘲的な微笑を浮かべながらそう言った。
「冗談はやめて、クラヴィス。あなたでも気付かないの?ジュリアスのサクリアの様子がおかしいってことを…。質も強さも…変でしょう?」
クラヴィスは彼女が心配していることが自分の思っていたことと全く次元の違うことだったのに驚いて、それから改めてジュリアスのサクリアを感じ取ってみる。
「……そういえば…いえ、私は今まで全く気付きませんでした…。」
「ジュリアスに何があったのかしら。おかしいのは今朝からなの。ゆ…昨夜は普通だったの…。どうしよう。私、何かジュリアスにしてしまったのかしら…」
さすがだな、とクラヴィスはこの少女が確かに女王であることを今更ながら確信した。
「…それはどうでしょうか…ああ、もうすぐ聖地に帰ってくるようです、陛下。…あれに直接会って確かめてみたらよいでしょう…。帰ってきたら…ここに真っ先に来る…ような気がする…。」
「クラヴィス…。ええ、わかったわ。待ちましょう。」
確かに近づいてくる光のサクリアを感じて、アンジェリークはそう答えた。
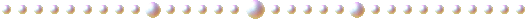
「クラヴィス、そなた…何故ここにいるのだ?」
ある思いを秘めてこの場に来たジュリアスは、アンジェリークの隣に意外な人物の存在を認めて本気で驚いたようだった。
「さあな…。」
「あ、ジュリアス。私がお呼びしたの。あなたのことが心配で…。」
「そうですか……申し訳ありません。急用でしたので、ついお伺いも立てずに無断で聖地の外に出てしまいました。どのような処分でもお受けいたします……。」
「……処分なんかしてたら、オスカーやゼフェルなんてとっくに守護聖クビになってるわよ。…もっとも、守護聖はクビにできませんけど…って、そんな事はどうでもいいのよ。ジュリアス。あなた体は大丈夫なの?」
女王の問いはジュリアスにとっては全く思いの外だったらしい。
「…は?」
「は?…って、顔色もよくないし、目も真っ赤だし、それにサクリアもなんだか変よ?」
「それは…」
ジュリアスは不調は自覚しているらしく、思わず口篭もった。その時、クラヴィスは言うまい、と思っていた言葉を堪らず口にした。
「アンジェリークは元気だったか…?」
「え?なあに、クラヴィス。」
女王が自分の事を呼ばれたかと振りかえる。が、ジュリアスはその意味をすぐに理解する。
「……クラヴィス、そなた、見ていたのかっ…?…あ…」
言葉と同時に、ジュリアスの半身が前に傾いだ。
「…あ、ジュリアス?どうしたの、ジュリアス?!」
「…ジュリアス!?」
屈み込むジュリアスに、女王のみならず、さすがのクラヴィスも驚いた。
「ジュリアス!しっかりして!」
「……だ、大丈夫です。少し……眩暈が…」
「そこの長椅子に横になって…!」
「も、申し訳ありません…。」
「話は後でいいわ。今はおやすみなさい、いいわね?ジュリアス。」
「…しかし、それでは…。」
ジュリアスのその様子を見て、クラヴィスが部屋を出ていこうとする。
「では、私はこれで…。」
「クラヴィス…、ありがとう、あなたのおかげで心強かったわ…。」
だがジュリアスは長椅子から身を起こして必死の形相で言う。
「待て、クラヴィス!……待ってくれ…。」
「……なんだ。」
「そなたに、話があるのだ……。」
「私はおまえの話など聞きたくはない…。」
「クラヴィス、私は…そなたに…あやま…ら…ねば…っ…」
そこまで言うのがやっとで、ジュリアスは胸をかきむしるようにして長椅子に倒れこんでしまった。顔面を蒼白にして、浅くかすれた呼吸をしている。
「ジュリアスっ?!きゃっ、しっかりして、ジュリアス!」
だがクラヴィスは、今のジュリアスの言葉の意外さにただ呆然としていた。
4.魔性の気配
「おそらく神経性の発作だと思います。陛下のお話から察するに、一時的に極度の緊張状態だったようですが、こんな状況が続くようだと本当に病気になってしまいますから、原因を取り除いてあげなければね。クラヴィス。」
とりあえずジュリアスが運び込まれた、宮殿の客用寝室から出てきたルヴァは、噛んで含めるような口調でそう言う。
「……なぜ私が…。」
「倒れる前に、あなたに話があると言っていたそうじゃないですか。」
クラヴィスはそれには答えず、ただ黙って今ルヴァが出てきた扉を見つめていた。
クラヴィスが部屋に入ると、ジュリアスは蒼ざめた顔色で寝台に横たわったまま、じっとクラヴィスの方を見た。そうしてから、付き添っているオスカーに何事か囁くと、オスカーは立ちあがって、クラヴィスにこう言った。
「クラヴィスさま。ジュリアスさまがお話したいそうです。私は席を外しますのでどうぞこちらにお掛けください。」
先ほどのルヴァの言葉が気になっていたクラヴィスは、無言でオスカーの勧めに従う。
「話とはなんだ。」
オスカーが部屋から出ていったのを感じとって、クラヴィスが口を開く。
「…そなたが言ったように…私は先ほど…彼女に会ってきた。」
ジュリアスがやっと、という感じでそう言った。苦しそうな口調は、体のせいだけではないのだろう、言い終わってからほうっと深いため息をついた。
「どうやって彼女の居所がわかったのだ?」
「…ゼフェルが偶然ディアに会ったそうだ…。それで…ゼフェルに頼んで…ディアに…会わせてもらったのだ…。」
「…だが何故、今になってそういう気になったのだ?」
「……わから…ない…。何故か昨夜…急に気がついたのだ…。」
「なに…?!」
「…昨夜…そなたの気配で…目が醒めた…。そして…思い出したのだ…あの…遠い日のことを…私は…何故…何も気がつかず…あのような…心ない仕打ちを…」
ジュリアスは両手のひらで顔を覆っていた。泣いているのだろうか…。このように心弱い彼を見るのはかつてないことである。
クラヴィスはジュリアスのその姿にひどく驚いた。サクリアの変調はこのせいだったのだろう。明らかにジュリアスはそのサクリアの基である自己の誇りを失いつつあった。
その時、クラヴィスは初めて気づいた。二人を覆う、わずかな魔性の気配に。
そうだ。そうでなければ二人同時にこんなやりきれなさに襲われるはずがない。
「もうよい、ジュリアス。少し眠るがいい。」
クラヴィスはジュリアスの額に手を触れ、闇のサクリアをわずかに送り込んだ。
ジュリアスの両手から力が抜け、顔から滑り落ちる。そして少し辛そうに眉根を寄せたまま、ジュリアスは安らかな寝息を立て始めた。
「私のこの力がこのように効くというだけで、もうすでにいつものジュリアスではないということだな。」
クラヴィスは眠るジュリアスの顔の涙の跡を指で拭うと、部屋から出ていった。
つづく