虜・2
5.ジュリアスは何処に
ふと気がつくと、ジュリアスはとても暗いところに横たわっていた。
起き上がってみようとしても、どこを押さえつけられているのか身動きが取れない。
苦しい。なにかの影に押し潰されているようで呼吸も満足に出来ないような気がする。何故、自分はこんな処にいるのか。何故こんなに苦しい思いをしなければならないのか。
…そうか。私の罪の故だ。人の心を踏み躙った私の受けるべき報いなのだ。
……それでこの罪が償えるなら、私は…誇りも、守護聖としての自分も、女王も、聖地も、何もかも捨てても構わないのだ…。そうだ。もう何もかも……どうでもいい…。
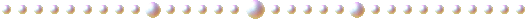
「ゼフェル!」
「お?クラヴィスじゃんよ…ちょーどいいぜ、ジュリアス見なかったか?外ではぐれちまって、しょうがねえから一人で帰ってきたんだけどよ、帰って来てるか?」
「……なんだと?!」
「…な、何だよ、なに怒ってんだよっ!いいじゃんか、訊くぐれーよ。」
「外ではぐれた、だと?」
「???おぅ、ディアのところに案内するって約束だったんだけどな、行く前にはぐれちまった。で、一応ディアのところに行ってみたんだけど、やっぱ来てなくてさ、でよ、結局前の陛下も都合が悪ぃってゆ〜ことで会えなかったんだけ…うわっ?なに迫って来るんだよ、クラヴィス!」
「だが、ジュリアスは彼女に会っていたぞ?!」
「彼女?」
「アン…前の陛下だ。」
「まさか?!ディアが言うには暫く用事で遠くに行ってて会えないって…」
「だがジュリアスは、おまえに頼んで陛下に会ったと…それに私の水晶球にも彼女が…」
そこまで言ってクラヴィスはあることに気がついた。水晶球に映ったアンジェリークの顔が、彼女が聖地から去ったあの日とまるで変わらない、若く美しい顔だったことを…。
「ジュリアスさまの容体はどうなんだ、ルヴァ。」
「なんと言ったらいいのか…症状は、眩暈と呼吸障害と…胸の痛みがあるようでした…でも、さっき私が看たときは意識だけははっきりしていたのですけどねえ。あ、オスカーは知ってましたっけ。…だけど今は、とても深い眠りについてしまって、全く目覚める気配がないのですよ。…そう、まるで心を閉ざしている…という感じに…。」
「あの…ルヴァさま…?」
「はい?なんでしょう、リュミエール。」
「クラヴィスさまが、ジュリアスさまは魔性に囚われていると…」
「なんだって?!」
「なんですって?それはいったいどういうことです?」
「いえ、わたくしにもはっきりおっしゃったわけではなくて…。今戻られて、水晶球でいろいろお調べになっているところですので…。」
「クラヴィス様が?…ずいぶんあの方にしては積極的だな…。」
「ふうん?じゃあ…深層心理…心の深〜いところに隠れてるいや〜な思い出でもほじくり返されてるんじゃないの〜?ジュリアスってば、半端じゃなく長く生きてるからね〜、いろいろヤな事抱えてると思うよ〜。ま、一種の悪夢っていうヤツ?」
「それはおまえの夢の守護聖としてのカンってやつか?オリヴィエ。」
「さあねえ、そうなのかな?」
「ではそれは、夢魔の仕業なのですか?」
「うーん、夢魔って言うのは、人間が勝手につけた名前みたいなもんだからねえ。でもまあそう言う感じのモンかな。私は美しい夢専門だからあまり悪い夢のことはわからないけどさ。で、なんにせよもしもジュリアスみたいに意志の強〜い人間を腕力以外でやっつけようと思ったら、私もやっぱりその手が一番有効だと思うよ。」
「ジュリアスさまが聖地の外に出られたことと、何か関係があるのでしょうか。オスカー、何かジュリアスさまからお聞きになってはいませんか?」
「いや。だがさっきチビどもから聞いた話だと、ジュリアスさまは前の女王陛下に会いに行かれたということだが…。ゼフェルが偶然ディアさまに会ったとかで…。」
「なんですって?でも前の陛下とジュリアスの間に何かありましたっけ〜?」
「さあ、わたくしたちは前の陛下のことはよく存じ上げませんし…。でもジュリアスさまはただ陛下が懐かしくてお会いしたかったのではないですか?」
「まさか。もしそうだとしても、ジュリアスさまがそんなに慌てて、しかも無断で聖地の外に行かれるような方だと思うか?」
「考えられないねえ。ま、普通のジュリアスだったら、の話だけどね。」
「ええ、オリヴィエ。どんな理由があるにしろ、いつも通りのジュリアスだったら絶対にそんなことはしないのは確かですねえ。」
「……つまり、今のジュリアスさまはやはり普通の、いつも通りのジュリアスさまではない、ということだな。だが…まさか、またあの時のように…」
「ソリティア?ま〜、今回は直接他の人に危害を加えそうな感じじゃあないけどねえ…」
「でも、今のジュリアスのサクリアの弱まり方は重大な問題ですよ。」
「そうそれ!直接じゃなくって間接的な方ね。今のままだと…もう…そうだねえ、明日あたりにはそろそろ影響が出始めるんじゃない?」
「なによりジュリアスさまのお体が心配です。かなり弱ってらっしゃるようですし…。」
「くそ!俺たちに出来る事はないのか?!ここで議論してても何の解決にもならんぞ。」
「……ああ、そうですね〜。じゃあ、一休みして、お茶にしませんか〜?」
「なっ…ルヴァ、そんな場合じゃないだろう!」
「落ちつきなって、オスカー。あんまり熱くなってるとろくなことになんないよ。ジュリアスのことが大事なのはあんただけじゃないんだからね。」
「ああ、…陛下もさぞや、お心を痛めてらっしゃることでしょうね…。」
「そうですね〜。お茶が済んだら陛下にもお伺いを立ててみましょうか。きっと今も何かお考えの最中だと思いますしね。」
「クラヴィスさまの方でも何か進展があったかもしれません…。」
「そうと決まったらお茶、お茶。リフレッシュしてまた仕切り直しましょ。」
「…おまえら、本当におめでたい連中だな…。(--;)」
ああ、こいつらはそう言う連中だった、逆らうだけ無駄だ…と改めて肝に銘じたオスカーだった。
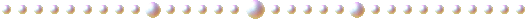
クラヴィスが謁見の間に入っていくと女王アンジェリークは半泣きの表情で、所在なげに立っていた。
「失礼いたします、陛下。」
「ああ、クラヴィス、よく来てくださったわね。私、今そちらに行こうとしてたところなの…。あの…ジュリアスは一体どうなってしまったのかしら。サクリアがもう消えてしまいそうに弱くて…わ…私…どうすればいいのか…」
「……おまえがそんな様子ではジュリアスの帰って来るところがないではないか、…アンジェリーク。」
「…いま、なんて?…クラヴィス…さま?」
「あれは今光の届かないような深いところに閉じこめられている。自分から光の力を持って立ち向えばいいのだがそれとて何故か封じられているようだ。だが…何かきっかけがあれば、まだ…立ち上がる力がある…はずなのだ。そのきっかけを作ってやれば…おまえにならできるはずだ、アンジェリーク…。」
「クラヴィスさま…私…っ」
「あれのいるところまでは私が導く。だがそこはもしかすると危険な場所かもしれない。それでも…もう…それしか考えられないのだ。やってみてはくれぬか…?」
「はい、やってみます…、クラヴィスさま。」
「そうか…。では頼む…。」
だがルヴァたちが謁見の間に入ってみると、すでに女王アンジェリークは玉座にもたれ掛かるようにして深い眠りにおちていた。しかもその横ではクラヴィスが崩れ落ちるように昏倒しており、傍らには水晶球が転がっている。
何が起きたのか、彼らにはまったく分らなかった。ただ余りの出来事に呆然と立ち尽くすのみである…。
6.眠りの中で
アンジェリークが目を覚ましたのは薄暗い場所だった。まわりには何もない…いや、誰かいる。誰かが倒れている。
「ジュリアスさま?!」
違う。クラヴィスだ。何故この方がここに…と、アンジェリークが思い出している間にクラヴィスが目を覚ます。
「う…ここは…?そうか…私まで来てしまったのか…。」
「クラヴィスさま…、大丈夫ですか?」
「…私は大丈夫だ…しかしこれでは聖地では大変なことになっているな…。」
「え?」
「おまえが眠っているだけなら私が状況を説明できた。だが私がここにいるということは、私も眠ってしまっているということだ。」
「あ…じゃあ、私たち二人とも倒れちゃってるって事なんですね。じゃあ、皆様とても心配なさっている…」
「そういうことだ。早く済ませて帰らねばな。」
「はい、がんばりましょうね。」
「……私はゆかぬぞ。」
「えっ、どうしてですか?クラヴィスさま。」
「私がお前と行っては、あらぬ勘繰りをされるだけだ…。」
「そ、そんな。ジュリアスさまはそんなことなさいません。」
「……普通ではないのだ、今のあの者の精神状態は。私が行けばこじれるだけだろう。」
「でも……。」
「私はここで待っている。ジュリアスはきっとこの奥の何処かにいるはずだ。おまえならきっと見つけることができる…あまり時間がない、さあゆけ!」
「……はい。行って来ます。きっとジュリアスさまを連れて帰ってきますから、待っていてくださいね、クラヴィスさま。きっとですよ。」
「……わかった。さあ、早く行って来るがよい。」
アンジェリークとこうして会話するのは、彼女が女王候補の頃以来かもしれないと、思わず苦笑したクラヴィスに、アンジェリークは微笑んで、踵を返し奥へと進んでいった。
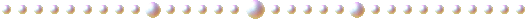
アンジェリークは進んでゆく。いや、本当に進んでいるのか。大体ここは何処なのか…ジュリアスの心の中なのか…夢の中ででもあるのか。クラヴィスに導かれるまま来てしまった世界。だが確かにわずかに光のサクリアを感じる。現実の世界でのそれより方向性のはっきりした力だ。しかしそれはどんどん弱まってゆく。何故なのだろう…? 以前彼が病に倒れたときもサクリアそのものには全く遜色がなかった。体のせいではない、心が侵されているのだ。
「ジュリアスさま!何処にいらっしゃるんですか!ジュリアスさま!」
だがわずかなサクリアでも、女王であるアンジェリークには敏感に感じ取ることができる。ついに、彼女はジュリアスの確かな気配を捉えた。
しかしアンジェリークはそこで驚くべき力を感じる。
「…闇の…サクリア…?!」
そのとき…暗闇の中に浮かび上がった光景がある。それは思っていたよりずっと優しい光景…それは悪意のない、だがとても切ない光景だった。
目を閉じて横たわるジュリアスのそばに一人の…少年だろうか…肩のあたりで切り揃えた黒髪の、優しく、哀しい目をした子供。少女のような風貌でさえあるが、それでもアンジェリークはその子供の正体を確信できた。
(クラヴィスさま…。)
その少年は、眠るジュリアスにさかんに何か話し掛けていた。消え入りそうに小さな声なので、アンジェリークはできる限り耳を澄ませて聞き取ろうとしてみる。
「ジュリアス」
少年は何度も名前を呼ぶ。
「ジュリアス。ごめんなさい、ジュリアス。ぼくはきみをきらいなんじゃないんだ。だけど、どうしてもきみとうまくなかよくできないんだ。
きみだけじゃない、ぼくはほかのひととなかよくすることができないんだ。だから、きみのことばをちゃんときくこともできない。そしてすぐきみをおこらせてしまうね。…ごめんね、ジュリアス。」
涙声である。たぶんいつもは決して口に出すことのできなかった本音であろう。この場所だからこそ言うことのできる、少年クラヴィスの本当の言葉に違いない。彼は何度もジュリアスに、ごめんね、ごめんねと呟いた。その言葉がやっと届いたのか、ジュリアスがうっすらと目を開く。
「……クラ…ヴィス…?」
「ジュリアス…ごめんなさい。」
「…何故、そなたが謝るのだ…私が…そなたに…謝らねばならぬのだ…私は…」
ジュリアスは震える声でそう言う。その声も、光のサクリアも今にも消えてしまいそうに弱々しかった。アンジェリークは彼らに声を掛けるべきか否かひどく迷った。いや、それより前に何故あの少年がここにいるのか。あの悪意のない少年クラヴィスが今のクラヴィスの言う『魔性』の正体なのか。
彼女は必死で考えた。アンジェリークは、『ソリティア』を知らない。この聖地にわだかまる、守護聖たちの捨てた悲しみや憎しみも知らない。だが考えれば考えるほど一つの答えに行き着く。クラヴィスの忘れた、いや忘れようとした思いが何かのきっかけであの少年の形になり、ジュリアスに働きかけたのだ。そしてジュリアスの中の最も弱い部分を呼び起こした。そしてジュリアスを苦しみから救おうとして送り込んだ闇のサクリアが少年と同調して、逆にジュリアスの心を奥にまで引き込んでしまったのではないか。
アンジェリークの目に涙が溢れた。なんと哀しい、なんと優しい者たちなのだろうか。きっと現実のジュリアスが目を覚ませば今までのような二人に戻ってしまうだろう。だがそれでもこの二人の心は、誰にも引き離すことのできないくらい強い力で引き合っているのだ。考え方も性格も、絶望的に違っていて理解などできないほどなのに…。
(やきもちを焼くのは、私のほうね…。)
アンジェリークは涙を拭きながらくすっと笑った。
「ジュリアスの謝りたい事はなあに?」
アンジェリークは思い切って彼らに近づいてそう言った。
「……女…王…陛下…?」
「じょおう…へいか…?」
アンジェリークは少年クラヴィスの頭にぽんと手を乗せ、軽く撫でながら言った。
「こんにちは、クラヴィス。あなたはやさしい子ね。」
「おねえさんがじょおうへいか?」
「ふふ。そうよ。ねえ、クラヴィス。ジュリアスはあなたのこと怒ってないって。それでね、あなたにあやまりたいことがあるんですって。聞いてあげてね?」
「…ジュリアス、ぼくのことゆるしてくれるの?」
「もちろん許すわよねえ、ジュリアス?」
「…何故…あやまる…悪いのは…私だ…」
「…ほら、また自分のことばかり言ってる!クラヴィスがね、謝りたいんですって!」
「……ごめんなさい、ジュリアス。なかよくできなくて、きみのいうことちゃんときかなくって、ごめんなさい…」
「クラ…ヴィス…?」
「ほら、許すって言ってあげなくちゃ、ジュリアス。」
「……クラヴィス…許すとも…いや、もう…とうに許していたのだ。…私は…」
「ありがとう、ジュリアス!」
アンジェリークはジュリアスの冷たい頬に手を当てながら訊く。暖かい手だ。
「よかったわねクラヴィス。で、ジュリアス、あなたの謝りたいことはなあに?」
「……陛下…、あなたにも私は謝らなくてはならない…。昔、あなたが女王候補の頃…クラヴィスと…逢う約束をしていた時…あなたは私に伝言を託した…。それなのに私は…クラヴィスにそれを伝えなかった…。それどころか…それがあなたの心を踏み躙っていた事さえ気づかなかった…。許してくれとは申しません…。ただ、謝りたかったのです…。」
その時、アンジェリークの姿が揺らいで、もう一人の少女が現れた。
「……ジュリアスさま…いいんです、私もいけなかったんです。クラヴィスさまの心を確かめるのが怖くって、あれきり、きちんと会って話せなかったのですもの。ジュリアスさまのせいだけではないんです、苦しまないで…。泣かないで、ジュリアスさま。」
「…陛下…あ、…アン…ジェリーク…?」
「私こそ、クラヴィスさまに謝らなくては…。」
「構わない…ジュリアスの言葉だけ聞いて、何もかも信じた…いや、確かめようともしなかったのは私も同じ…自業自得なのだ。もう、誰も恨んでも憎んでもいない…。」
そう言ったのは紛れもない、あのときのクラヴィスだ。
「…クラヴィス……では、私のことを…」
「許すも許さぬもない、ジュリアス。もう気に病むな。」
「…よかった。クラヴィスさま、ジュリアスさま、ありがとうございます。」
「……ふっ。私もおまえに謝らなくてはいけないと思っていた。だがもうよいな。」
「はい、私も…初めから誰のことも恨んでもいませんでしたから。」
そうして、クラヴィスとアンジェリークは微笑むと、ふっと姿が見えなくなった。
「……今の…は…いったい…?」
あの頃のクラヴィスとアンジェリーク。いったい自分は何を見ていたのだろうか。何故このようなところにいるのだろうか。幼いクラヴィスは…あの二人は…幻か?いや、それにしては暖かい手だった。心が癒されたのが確かにわかる。
「私は…そうだ、私は確かに罪を犯した。だが、それに囚われていては前に進むことが出来ない。罪を犯したなら、もう二度と繰り返さぬよう、誠心誠意、出来る限り償えばよいのだ。いつまでも罪の虜になっていてはいけない。自分を卑下してはいけない。どんなことがあっても、私は生きている限り自分の誇りを手放してはいけないのだ。私の司る誇りは決して自分自身を誇ることではない。私は女王の統べるこの宇宙の、その光をこそ誇るのだ。そしてそれが自分の誇りになるのだ…!」
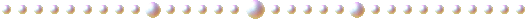
「う〜。あれっ?私…あ、クラヴィスさまっ?」
「……うむ。いつの間にか眠っていたようだ。」
「あれ?…さっきまでジュリアスさまと…あっ!」
「ん?ジュリアスと会うことが出来たか?」
アンジェリークは『魔性』の正体を思った。クラヴィスはやはり知らないのだ。でも、私も何か忘れている。ジュリアスさまと小さなクラヴィスと…あと…誰かがいたような気がするのに…。なんにせよ、とりあえず今は『魔性くん』のことは黙っていよう。アンジェリークはそう思った。
「ジュリアスさまは…きっと大丈夫……ああ、ほら、すぐ帰ってきますよね。」
「ん?……ああ…そうだな。さあ、私たちも帰ろう。…お手を、陛下。」
立ちあがったクラヴィスがアンジェリークに手を伸ばすと、アンジェリークは微笑んでその手を取った。先程薄暗かったその場所は、今はまばゆいばかりの光であふれている。
7.帰還
「おはようございます。お加減はいかがですか?クラヴィスさま」
「……私はなんともない、と言っただろう、リュミエール。」
昨日女王と、二人の守護聖の昏睡によって大騒ぎになった聖地も、今日はいつものように平和な朝を迎えた。ジュリアスだけは疲労が激しくまだ臥せっているが、それでも口のほうはもう充分過ぎるくらい回復したらしい。早速、廊下でふざけていた子供たちがお小言を食らって、いつもの如くゼフェルが悪態をついた。
「も〜、ディアのとこになんかぜって〜連れて行ってやんね〜!」
一方、女王アンジェリークは大泣きのロザリアに散々叱られてしまった。そして当然それはクラヴィスにも及んだ。
「帰って来られないかもしれないところに陛下をお連れするなんて、常識がなさ過ぎますわ!少しは考えてくださらないと!」
もちろんクラヴィスに人並みの常識など通用するわけもないことは、ロザリアも承知の上だったが。
「だけど、ジュリアスが外界で逢った方はどなただったのかしら…。」
ジュリアスの病室になっている宮殿の客間には、女王アンジェリークと、彼女に無理やり連れて来られた闇の守護聖の姿があった。
「おそらく……私の弱った心が夢か幻でも見せたのでしょう。それに、私は聖地の外に行った記憶すら確かではないのでよく覚えていないのですよ…」
「…でも、クラヴィスは水晶球でその様子を見ているのよ。ねえ、クラヴィス?」
「……水晶球の映像は、心を通して見るものですよ…。」
「じゃあ、ジュリアスの心を通して見た、というの?クラヴィス。」
「……そう申せば、最初に目がさめたときに感じたのはそなたの気配であったな、クラヴィス。あれはいったいどういうことなのだ?」
「……知らぬ。おまえが勝手にそう思っただけだろう…」
「そうはいかぬ。そなたもしかして我々の寝室を…」
「知らぬと言っている。意識過剰ではないのか?」
「なにっ?!」
「ああ〜んもう、やめてくださいってば二人とも!」
(まったく、あそこで見た心温まる光景は、いったいなんだったの?感動して損したのかなあ、私。ただ自分がスッキリすればいいのかしら、この人たちって…。)
結局サクリアの弱まっていた間のジュリアスの記憶も定かではなく、『魔性』についても女王アンジェリークが「悪意なし」と、太鼓判を押したことで不問にされた。だがそのアンジェリークすら最後のほうの記憶がない。要するに完全に事件を把握しているものは誰もいないということだ。
(それにしてもこの二人って…)
ひたすらお互いに謝りつづけていたあの二人を目の当たりにしているだけに、いくらなんでも多少は関係改善が見られるだろうと思ったのだが、やはり甘い幻想に過ぎなかったのだろうか。アンジェリークは思わず深いため息をついた。
「色々ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、陛下。」
「…いいのよ。いつも助けてもらってばかりだから、たまには、ね?」
「私はまだ礼を言ってもらっていないな。」
「………色々世話を掛けたようだな、クラヴィス。礼を言うぞ。」
「あまり陛下に心配をかけるな…。」
「ああ、すまなかった…。」
「私はいい…。…では、私はこれで…。」
クラヴィスが席を立つ。それを横になったままのジュリアスが目で追う。ちら、と振り返ったクラヴィスの目が、少し笑ったように見えたのは気のせいだったのだろうか。もしかしてこの二人は、何があったのか全部覚えているのではないだろうか。それを暗黙の了解の上で忘れた振りをしているのではないだろうか…。
「どうした、アンジェリーク。」
「……いいえ、ジュリアスさま、何でもありません。」
「まったく、ここでは私とクラヴィスの腐れ縁のせいで色々おかしなことが起きてしまうな。色々ありすぎるのだ…あれも、私も…。ふふ…。」
「ジュリアスさま…?」
もしかして、と言おうかと思った言葉をアンジェリークは飲み込んだ。
「またそなたを泣かせてしまったようだな…。」
「いいえ、今度は大丈夫でした。クラヴィスさまがついていてくださったので…。」
アンジェリークは思わずそう言ってジュリアスの顔を覗き込んだ。
「そうか。まあ、たまにはあれにも働いてもらわなくてはな。」
ジュリアスはそう言うと、嬉しそうに笑った。ああ、そうなんだ。この二人は、これでいいんだ。そう思うとアンジェリークはあの場所でしたようにジュリアスの頬に触れた。
「暖かい手だ…。それに、何故だかとても懐かしい。」
アンジェリークはそのまま黙ってジュリアスにくちづけた。
その唇の確かな暖かさをいとおしむように…。
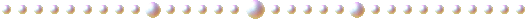
クラヴィスはもう一人の金の髪のアンジェリークのことを思っていた。またいつか逢える、そんな気がする。その時になったら、あの日言えなかった言葉を口にしてみようか、と柄にもなく考えてみた。
それにしても…恋故にクラヴィスは心を深く閉ざし、ジュリアスは心の弱さを知った。
「恋…か。」
本当の『魔性』は恋かもしれない。クラヴィスはそう思いながら水晶球を透かして見る。そこに映ったのは…明るく微笑む少年の日の自分…。
「そうか。おまえは今、幸せなのだな。」
そう言うと、クラヴィスは立ちあがって執務室の窓を開け放ったのだった。
おしまい

 創作目次へ
創作目次へ 